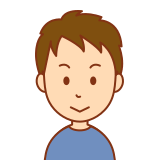
今回は、取り入れ方に試行錯誤されている方も多いと思われる
【PDCA】です。
宜しくおねがいします。
結論
「ゴール=目標」を設定するとPDCAは取り入れが
スムーズになる

目標ってケアプランの「長期目標」と「短期目標」でしょ?
そんなの、ちゃんと設定して立案してるよ。
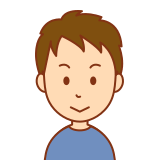
そうですね。
もし、これからの内容をすでに実行されている方はPDCAの範囲を個別からフロア全体、事業所全体と拡げても良いかもしれません。
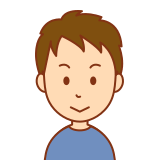
ひとまず、今回は基礎的な利用者一人あたりに対するPDCAと捉えてください。
なので「目的」ではなく「目標」としています。
PDCAとは
基礎部分なので、簡単に記載します。
P=計画、D=実行、C=気付き、A=評価
P=計画(Plan)
ある物事を行うために立てる計画です。
商店であれば、『新商品を売る』ために
- 「○個売るために広告をつくる」
- 「叩き売りをする」
- 「店頭で試食をする」
などです。
介護場面であれば、具体的なサービス内容を記載するところと思います。
例)・・・毎朝、起床の時に介助で起こす
D=実行(Do)
実際の行う行動です。
P=計画で立てたうち、3.「店頭で試食をする」を選んだ場合
実行するので、当てはまることになります。
また、実施に対して得られた結果も含まれます。
・店頭で試食を勧めたところ、二人に一人が試食をし新商品が予想以上に売れた。
同様に介護場面でも、実行した内容です。
毎朝、起床時に介助を行った。
・いつも通りにスムーズに起きれた。
C=気付き(Check)
実行した際に見られた現象に対して文字通りに気付いた内容です。
店頭での試食のため回避できず食べた結果、購買意欲に働きかけることができた。
駐車場から美味しそうな匂いにつられる人がいた。
など、様々な点を自由に挙げることができます。
介護場面でも、
特に体調に問題がない。
起きる時の介助と方法が上手くいっている。
など、その時に気付いた内容で予測でも充分な部分です。
A=評価・変更(Action)
実行と気付きを踏まえて、次の計画につなげる内容です。
次回も同じような店頭試食にしてみよう。
次回は店頭試食の時間帯に気を配って行ってみよう。
介護場面の場合は、
このまま、同じ生活リズムで介助すると起き上がりは維持できそうだ。
同じ時間で違う介助方法では、介助量が変化しないだろうか?
余談:昔習ったPDA
工業分野の製造サイクルで使われていた
20年以上前に高校で設備・管理という授業を受けた時には、現在のようなPDCAではありませんでした。
当時はPDAといって、C=気付きの項目が入っていない3要素で製造プラントの管理を行っていました。
気付きが入ったことによるメリット
PDAは、規模や期間が大きなサイクルで行う場合には実行途中から評価を行うことができた反面、素早い思考が求められる短期間・小規模の場合に適応しづらいという点があったようです。
C=気付きが取り入れられたことにより、短い期間でも見直しをする時に評価しやすくなったと言われています。
介護場面のPDCA
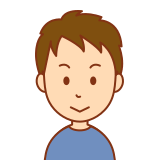
では、実際に介護現場でPDCAがどのように使われているのか
考えてみたいと思います。
殆どはケアプラン作成ごとに見直すPDCA
基本的にケアプランの見直しごとにPDCAを再設定しているものと思います。
しかし、この見直し間隔だと期間が長く、内容が見えにくくなってしまいます。
具体的に期間の差は以下のとおりです。
見直し期間の差
リハビリや栄養の見直しは最短1ヶ月です(初回の2週間見直しを一旦除きます)
ケアプランの部分によっては6ヶ月有効な見直しもあります。
大きな体調の変化が見られない維持を目的とした利用者でもプランによる見直し期間の差は大きくなります。

かといって、ケアプランを短い期間に区切って見直すなんて
手間を増やすことはできないよ。
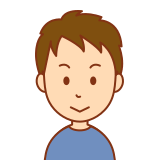
そこまでしなくても大丈夫ですが、その前に
ちょっと確認しておくことがあります。
P=計画に長期・短期目標を設定していないか
少ないとは思いますが、ケアプランの長期・短期目標や総合的な援助の方針などを
P=計画の部分に当てはめてしまうと、「目標と具体的なサービス内容」の2つが計画部分で混ざってしまい見えにくくなってしまいます。
日々の業務とケアプランをPDCAに反映させる場合には、2つの目標が重複してしまっていないかを確認してください。
目標を【ゴール】とするもう一つのPDCA
ここからは、PDCAの使い方になります。
長期と短期目標をゴールに設定する
はじめの新商品に関する例を思い出してください。
新商品を売ることが目標でした。
この目標を「新商品を○個(ケース)売る」と目標を設定して、PDCAの上に設定したらどうでしょう?
売上目標○個

立案される計画・実行・気付き・評価全てに対して、何個売れたのか?
という視点が加わります。
同じようにして起床介助の例で、もし目標を
『毎朝の起床介助で介助量が増えないように維持する』設定したら、
介助量の目安は何か?時間?支える力?
といった視点が加わります。
ゴールを目指したP=具体的なサービス内容
視点をあらかじめ定めておけば、P=計画の部分に入る具体的なサービス内容も
合わせて明確にすることができます。
P目標を縦に二分割する
特に具体的なサービス内容をP=計画に取り入れる時にPDCAの表を作りP欄を縦割りにします。
二分割された縦左を具体的なサービス内容、右側を実行頻度とするとより明確にすることができます。
ワンポイント
目標が「○○機能維持」と曖昧でも、ゴールとして欄外に書く際に「どの程度の期間」維持するのか、「どの程度の介助量」を維持したいのかと客観的に比べることのできる目安を作ることで充分活用できます。
ゴール設定のメリット
ゴール=目標を欄外に記載することで得られるメリットは以下のとおりです。
- 具体的なサービス内容が明確になる
- 見直しをするときの基準が分かりやすくなる
- 「介助量が増えた/減った」曖昧な表現から「介助の有無で〇〇分の違いがでる」
など
ゴール設定のデメリット
PDCAにゴール=目標を設定することのデメリットは以下のとおりです。
- サイクルに慣れていくまでに多少の時間がかかる
- 定められた関わり以外の場面に対する”気付き”に多少のトレーニングが必要となる
PDCAに慣れるためのトレーニング方法
PDCAを取り入れて慣れるまでには、多少時間がかかります。
慣れるまでの時間を少しでも短くするための方法です。
月単位のPDCAを週単位と日単位にしていく
ケプランの場合は、1月ごとのモニタリングまたはミニカンファと呼ばれる会議の際に見直しができるようにケアプランから逆算していきます。
逆算することによって、自然と目安が明確になっていきます。
週単位は業務の分割が可能
ケアプランと連動しないような内容のPDCAであっても、週間単位であれば簡単な内容で作成することと見直すことは可能です。
その際には、日々の業務と同様に【観察】を絡めるとトレーニングになります。
日々の業務に関するPDCA
日々の業務に関するPDCAは、利用者との関わりよりも職員同士のコミュニケーションや後進育成などと【観察】を絡めるとハードルを下げてトレーニングすることができます。
アセスメントにPDCAを取り入れる
利用開始時や定期的なアセスメントそのものにPDCAを取り入れると視点を変えやすくなります。
方法としては、
- 評価する目的をゴールとして作成
- はじめのうちゴールは利用目的の転載も可能
- 目的(介護利用の希望)と生活状況を見比べる事をP=計画にする
- 事前情報と実際の違いやアセスメントする内容や方法、場面がC=気付きになっている
- 環境の差や調査時点と利用開始時点の期間差などをA=評価としてP計画につなげる
と、いった順ですすめていきます。
評価そのものがサイクルとなるので、見落としをしてもすぐに修正できます。
書籍紹介
今回、記事作成に当たり下調べ中に出会った一冊です。
「P」・「D」・「C」・「A」それぞれの単元が短いことと
カラフルな内容で、全体に簡潔で読みやすくなっています。
著者の岡村さんは「D」行動が一番大切と書かれています。
私自身は介護現場の場合には、「P」次第で「D」をコントロールすることができると考えています。
介護現場で活用方法には踏み込まれていませんが、
目標=ゴール設定に踏み込んであるため、実行「D」後に訪れる
面倒にされがちな気付き「C」がやりやすくなります。
PDCAを業務に上手く反映できない方や回し始めると
気付き「C」で躓きやすい方は、一度手に取ってみてもよいかもしれません。
私自身も行ってきた内容に自信を持つことができ、
更にPDCAを新しい視点で見る機会を得た一冊でした。
まとめ
- PDCAはゴールを設定すると計画が明確になる
- ゴールが明確にできると計画と頻度も明確にできる
- 計画が明確だと見直しも明確にすることができる
![自分を劇的に成長させる!PDCAノート [ 岡村拓朗 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7400/9784894517400.jpg?_ex=128x128)

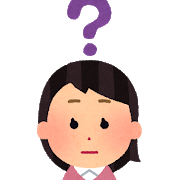
コメント